
福井県内で稲作の専業農家をやっています。
最近豪雨による水害が各地で発生していますが、うちでも十数年前に福井豪雨が発生し、私たちの地域の田んぼも大きな浸水被害を受けました。
そのため、毎年、梅雨から台風シーズンにかけて気が気ではありません。
行政でも、堤防の整備や補強などの対策を行っていますが、上流では手入れされない山林や耕作放棄地、休耕田なども増えていると聞いており、以前よりも大雨時に雨水が河川に流れ込みやすくなっているのではないかと心配です。
最近、大雨が降ると田んぼにいったん水をため込んで、河川に流れ込む水の量を調整する取り組みが新潟あたりで行われ、一定の効果を挙げていると聞きます。
「田んぼダム」というそうですが、排水口から出る水の量をどう調整するのでしょうか?
また、ダムのようなイメージで田んぼに水をため込むと、稲の生育に影響が出るのではないかと心配になります。
中干しの時期は田んぼを乾燥させないといけないので、その場合はどうするのでしょうか?
(福井県・前田さん/仮名・50代)












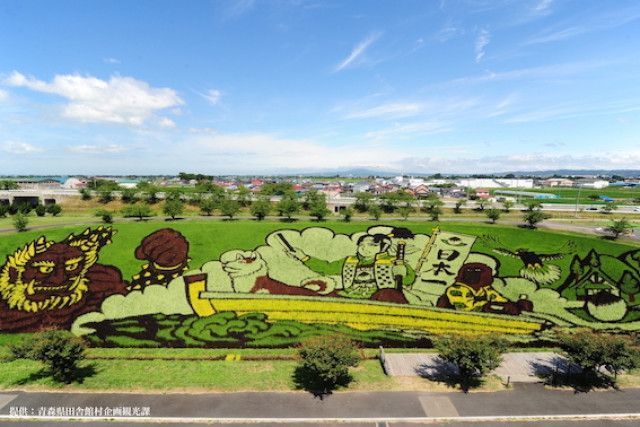
















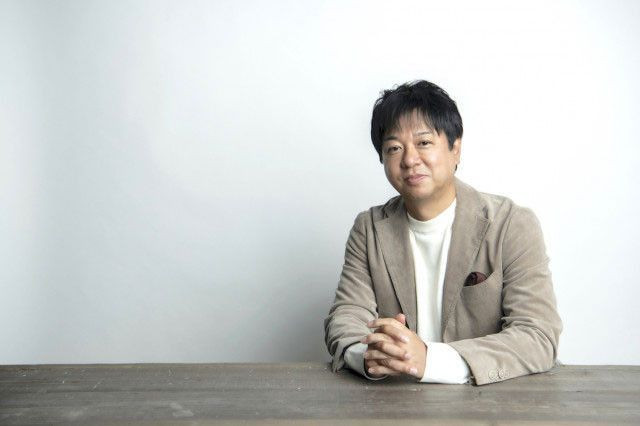







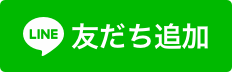
吉川夏樹
新潟大学 教育研究院 自然科学系 農学系列、農学部農学科教授
水田を利用した「田んぼダム」で水害を防ぎましょう!
近年、毎年のように大規模な水害が発生していますが、その原因として、雨の降り方の変化をはじめ、農地転用や、耕作放棄地の増加などが考えられます。
水田のあぜは、雨水を一時的にため込む機能がありますが、水田が減少すれば、この機能も弱体化し、水が一気に河川に流れ込み、氾濫につながります。
明治以降の河川整備は、水の流れを押しとどめるために、堤防設置などが主流でしたが、ここへきて異なる動きが見られます。私が専門とする「田んぼダム」も、そのひとつ。
「田んぼダム」は水田の排水口の口径を狭める「仕掛け」を設置して、大雨が降ったときに水田から排水されるピーク時の流出量を少なくする仕組みです。
遊水地のように河川の水を水田に導いて貯水するのではなく、水田に降った雨水を、一時的にとどめる仕組みです。排水口からの水量を調整する「適切な仕掛け」を設置すれば、水田から水があふれるリスクを低くできます。
排水口を完全にふさいで、全降水量を水田にためてしまった場合、300mmの雨が降れば、水田の水深は30cmになりますが、田んぼダムは排水しながら雨水をためるので、水深はもっと浅くなります。私が開発した仕掛けは、30年に1度の大雨(170mm/日)が降った場合でも、排水量を7割程度カットできるように設計しています。
新潟県で記録された1日あたり180ミリという、50年に1度クラスの大雨が降ったても、ピーク時の水深は11cm程度。田植え直後ならイネが水没しますが、水害が起こりやすい梅雨以降であれば、稲も水没しない程度に成長しています。
新潟県や農協とともに、水田への影響を検討した結果、仮に1年に1回、11cm程度の深さの水に浸かっても、生育にはほとんど影響がないことがわかりました。
しかし、最近では「不適切な仕掛け」を使った装置も出回っているので、注意が必要です。私の設計した装置では、排水口に取り付ける「堰(せき)板A」とは別に、内側にもう1枚、穴が空いた板Bを設置できる仕組みになっています。
水深を調節するには、排水マスの前面にある堰板Aで行いますが、水田から水を抜く中干し時には、これを外して水を抜いたのち、これとは別に、マスの内側に、穴があいたもう1枚の板Bを設置します。
この装置だと、小雨程度では田んぼダムを実施しても、雨水は常に排水されっぱなしになるので、水田にはたまりません。
大雨で水深が増えて、排水マスに流入する水量が、堰板の穴から排出できる水量を上回ったときに初めて、田んぼダムの効果を発揮します。要するに、大雨が降った場合だけ効果が現れるので、通常の中干し期の管理と変わりません。
一方、堰板の構造が異なる不適切な装置の場合、小雨であっても、水田に水がたまってしまううえ、中干し期には水を抜けない状況が起こりやすくなるので要注意です。
田んぼダムは「適切な仕掛け」を採用すれば、イネへの影響はほとんどありません。ここに田んぼダムを推進してきた新潟市が発行するパンフレットがありますので、ご参照ください。