
近代まで日本の農業は、先祖代々受け継いできた農地を農家のあとつぎが継いでいく形で発展しましたが、戦後の民主化に伴って、約80年かけて大きく様変わりしました。
農家に生まれても会社に就職し、定年退職後に農業を始める人もいれば、非農家出身であっても農業の世界に挑戦する若者もいます。
農業をひとつのビジネスとしてとらえ、起業しようとする挑戦者にとって、最初の壁になるのは、好条件の農地との出会いや、農機や設備の購入にかかる初期投資。
非農家出身者がこの問題を克服するには、引退する農家から土地や設備を丸ごと譲り受けるのが理想ですが、第三者による事業承継は実例が少ないのが現状です。
水稲種子農家に生まれ、事業承継士としても活動する伊東悠太郎さんは、第三者承継があたりまえになることで、日本の農業が活性化するとして啓蒙活動を行っています。
今回は、石川県の農業法人に雇用就農したのち、独立を目指して隣の福井県で農業法人の代表をつとめることになったグリーンファーム角屋(すみや)の斎藤貴さん(46歳)と、前代表・坪田清孝さん(72歳)と2回に分けて座談会形式でお届けします。
この記事のポイント
・集落営農組織の設立から15年で迎えた危機
・第三者承継ができなければM&Aも考えた
・地縁には縛られない。それだけ限界を感じていた!
・最初に決算書を見せられた
・儲かる農業、楽しい農業にシフトすべし。
・法人従業員ののれん分けによる第三者承継
集落営農組織の設立から15年で迎えた危機
斎藤さんは、もともと埼玉県の出身ですが、高校時代に行った農業実習の経験から、農業を志すようになりました。卒業後は石川県の農業法人に就職して20年間米作りに携わり、取締役まで昇進しましたが、あまりにも多忙で、心身ともにストレスを抱える日々に疑問を感じるようになり、独立就農を目指すようになりました。
一方、グリーンファーム角屋は、高齢化による担い手不足が深刻化していた福井県あわら市の角屋地区で、16戸の農家が集まって1999年10月に設立された集落営農組織です。米や麦、大豆を中心に営農していましたが、設立から15年ほど過ぎて、組織を構成する農家の世代交代が進まず、農地管理がままならなくなったことから、経営者候補を外部から招くことにしたのです。

第三者承継ができなければM&Aも考えた
伊東悠太郎:齋藤さんは2023年にグリーンファーム角屋の経営権を引き継いで、代表取締役社長になられたわけですね。今日は現会長の坪田さんにもご同席いただいて、どういった経緯で第三者承継に至ったのか、お話を伺います。
坪田清孝:私は元々、農林水産省に入省し、北陸農政局、東海農政局を経て、芦原町(現・あわら市)で勤務してきました。全国的に見ると2007〜8年ごろに集落営農組織の立ち上げが進んだかと思いますが、当地区では、その動きに先駆けて1999年に集落営農組織を立ち上げました。
ですから、早い段階で高齢化・担い手不足が顕著になってきたんですね。そこでたまたま縁があって2016年に齋藤さんと出会いって、来てもらうことになりました。2019年には、従来の農事組合法人から事態に応じて対応可能な会社法人である株式会社に組織変更し、代表取締役となりました。4年後の2023年2月、彼に社長職を譲り、現在は会長という立場です。高齢化・担い手不足は全国の集落営農が抱える課題だと感じております。
斎藤貴:私は、こちらに来る前は隣の石川県の農業法人で20年ほど勤務していました。当時は取締役という肩書きもあり、ゆくゆくはその法人の代表を譲り受けるのかなという気持ちもありました。しかし、その法人での仕事は多忙で、大切な家族との時間も思ったように取れず、精神的にしんどさを感じていました。
このままではいけないと思い、退社をして家族と過ごす時間を取るようにして、独立就農を目指して転職活動をしていくなかで、後継者を募集していたグリーンファーム角屋と出会い、ここでなら家族との時間も大切にし、やりたい農業も実現できるのではないかと思って、移住し、そして第三者承継での就農を決めました。
伊東:お二人が出会われたきっかけをもう少し具体的に教えていただけませんか?
坪田:2016年当時、自然農法に興味があって、研修会がきっかけで県の普及指導員と出会いました。ちょうどその頃、組織を受け渡す人がいないかを考え始めていた矢先だったので、たまたま県の職員から「独立就農を考えている若者がいるよ」と紹介を受けたんです。すぐにコンタクトを取って、2週間のインターンシップを経て、「彼なら大丈夫そうだ」と思って、次の1年間の研修雇用期間中はお互いの相性はどうかとみていました。当初は、第三者承継が難しければ、いわゆるM&Aでどこかの企業に買ってもらうことも頭の片隅にありました。
斎藤:坪田さんから「第三者承継をやってみないか」と声をかけられて、実際にグリーンファーム角屋の圃場を見にきて、営農するための機械や設備が一通り揃っているのに、誰も継ぐ人がいないんだと驚いた記憶があります。

地縁には縛られない。それだけ限界を感じていた!
伊東:集落営農と言えば、まずは、その地域に住んでいる「地縁」を前提としたバトンパスだと思うのが一般的。地域外の第三者に継承させるという考えが集落内で合意を得るのはなかなか難しいのではないかと思うのですが?
坪田:普通の人は難しいと思うでしょうけれど、うちは地縁と言う発想に縛られていませんね。その発想ができるかが大きな違いだと思いますよ。
よく、第三者承継をどうやって成功させたのか聞かれるのですが、集落の機能やコミュニティを維持していくうえで、「これ以上、自分たちでは無理だ、もうなんとかしなければ」と限界を感じていたのが、逆に言うと第三者承継を成功させた理由です。
伊東:親世代の間では地縁にとらわれて、集落を構成する農家の子供が継いでくれるのではないかという淡い期待を持っているところも多いでしょうね。
坪田:それは時代の流れでしょうが、親の世代が後継者として期待していた子供世代は、県内外で農業以外の仕事に就職して頑張っています。福井県の集落営農組織では、若者は基本的に農業をやりたがりません。そりゃそうですよ、儲かっていなければ誰もやりたくないですよね?
一方で、定年就農でなんとかしようという発想もありますが、定年の年齢がどんどん伸びていくなかでそれも難しくなってきています。組織を立ち上げた時とメンバーは変わらず、平均年齢だけが上昇しているのが現状でしょう。だからこそ、地縁にとらわれないという発想が大事だと思うわけです。
伊東:今回も、よく言えば運命の出会い、悪く言えば偶然の出会いです。とはいえ、ラッキーだったとまとめても意味がないので、やはりこういった出会いの場、マッチングの場というのは、仕組みとして創り上げていくべきだと思いますね。
斎藤:私も前職の農業法人を辞めて転職活動をしましたが、こういった第三者承継で後継者を募集している経営体の情報は全然ありませんでした。実際はそういった経営体は山ほどあるはずなのに、本当にもったいないなぁと痛感しています。まずはマッチング機能を、行政やJA、農業委員会などで担って欲しいと思います。
伊東:関係機関にその機能を求めたい一方で、後継者がいない経営体側からもどんどん発信していくべきですね。後継者がいないことをオープンにするのは勇気がいることですが、それではいつまでも事態は好転しません。そういう経営体が増えてくれば、マッチングも成熟していくんじゃないかと思います。
最初に決算書を見せられた
伊東:話は横道に逸れますけれど、坪田さんは第三者承継がうまく行かなければ、M&Aの可能性も考えたとおっしゃっていましたが、集落営農組織同士を合併して、組織を広域化するようなことは考えたりしませんでしたか?
坪田:いわゆるメガファーム構想ですね。集落単位の営農組織を合併すると集落を結びつけているコミュニティ(絆)が無くなってしまうと恐れがあります。農村集落をいかに守っていくか、と言うことを考えた時、第三者である齋藤さんが集落の中に加わって、溶け込んでいくことが大事なんです。
斎藤:僕自身、ここに来るまで集落営農組織にあまり良いイメージを持っていなかったんですね。というのも、これまでに見聞きしてきた集落営農組織のなかには、ずさんな経営管理によって赤字が膨らんでいる印象があったから。
グリーンファーム角屋では最初の段階で財務諸表を見せてもらったので、適切に管理されていることが分かって、経営全体が見通せるなという感覚になったんですね。ですから、数字としては大丈夫そうだなと。
伊東:コロナ禍で移住ブームが注目されましたが、農村の集落(営農組織ではなく、集落全体)というと排他的で、よそ者を受け入れにくい空気があるのも現実ですが、その点、不安はありませんでしたか?
斎藤:人間関係はまったくのゼロから始まるので、集落の人と馴染めるかは心配でした。前職でも、1年間はあいさつしても、近隣の人はなかなか相手にしてくれないという経験がありましたし。
だから、農業に一生懸命取り組んでいる姿を見せれば、いつかは周りがちゃんと見てもらえるだろうと思っていましたね。もし1年続けて、この集落に合わなければ、その時に(退職を)考えようと思っていました。でも、坪田さんが地慣らしをしてくれていたので、集落に溶け込むのはスムーズに行ったと思います。
坪田:最初のインターンシップとその次の年間を通じた研修雇用を行って、とにかくコミュニケーションを取る努力をしましたね。集落営農は地域のリーダーの考え方が重要ですから、リーダーの指導力で右にも左にも変われるんです。
うちは集約された農地もあり、農機具も施設も一通りは揃っていて、あとは経営を継いでくれる「人」だけの問題だったんですね。2019年からは年間雇用という形で働いてもらっていますが、彼が最初に来てから、代表になるまで7年かかりました。それだけの時間をかけて準備を進めたのです。
集落内はもとより、農家仲間やJAに彼の存在を知ってもらうために、すぐにJA青年部に入ってもらったし、市や県の会議にも出てもらって顔を売りました。農業関係の新聞でもどんどん取り上げてもらって、意識的にPRしてきたのです。
儲かる農業、楽しい農業にシフトすべし。
伊東:集落営農では、みんな総出で作業して、労賃で構成員に還元すればOKという考え方があります。一方で、人口減少社会ではそのやり方自体に限界があるとして、齋藤さんのような方を専従雇用するやり方もある。どちらにしても、省力化して少ない人数でまわしていく経営に変える必要があると思うのですが、その点はどうでしょうか?
坪田:近隣にも中核農家がたくさんいて、そこはしっかり後継者がいます。一方で多くの集落営農組織では後継者がいない。この違いは何かというと、やはり儲かっているかどうかに尽きます。集落営農から「儲かる農業」にシフトできるかどうかがポイントです。
伊東:集落営農には「農地を守るため」と言う目標で結ばれている組織が多いと思うので、そうなると「儲かる農業」には否定的な声も出てきませんか?
坪田:「農地を守る」という視点から「儲かる農業」へシフトしなければ、未来はないでしょう。と一言で言っても、問題はそんなに簡単ではありません。
特に、常時雇用するとなると、財源をどう確保していくか?と言う議論になりますし、地代や労賃の見直しも当然必要になってきます。福井県は雪国ですから、冬場の仕事を創出することも考えなければなりませんし、収益性の高い農業に転換していくためには、組織内での合意形成が非常に大事になってきますね。
斎藤:やはりサラリーマン並みの所得がないと、継ぐという決断は難しいですね。それと、楽しいと思えるかどうかが大事。過去には、農業が好きで始めたのに、農業がつらく感じる時期がありました。我が子が継いでくれたらありがたいですが、誰か次の世代にバトンを渡す時に、私自身が農業をやっていて楽しんで見えることが大事だと思います。
伊東:なるほど。私もまだ小学校に入学する前の小さな息子がいるので、そのご意見はうなづくところが多いです。次回はこれからもっと第三者承継を広めていくために、どんな工夫が必要か話していきましょう。
後編に続く
この記事の執筆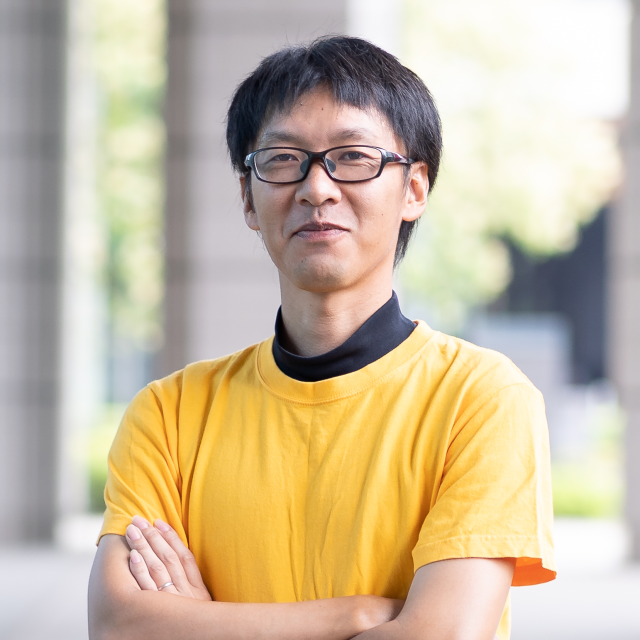
伊東悠太郎
富山県の水稲種子農家として生まれ、2009年にJA全農に入会。『事業承継ブック』の発行や、営農管理システム「Z-GIS」の開発などに携わる。2018年に退職し、実家を継いで就農。YUIMEでは専門家としてさまざまな農家の悩み相談にアドバイスを送るほか、農家の事業承継に関する連載を担当。近著『農家の事業承継ノート』、『今日からはじめる農家の事業承継(2万人の跡継ぎと考えた成功メソッド)』(いずれも竹本彰吾氏との共著/家の光協会)




























